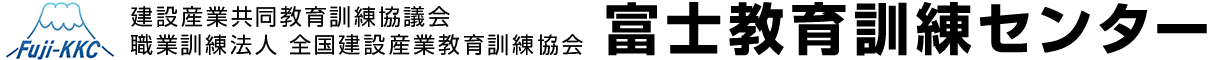助成金の紹介
富士教育訓練センターで認定職業訓練を受講し、条件を満たす場合、雇用関係助成金の人材開発支援助成金(人材育成支援コース(賃金助成・経費助成))、人材開発支援助成金((建設労働者認定訓練コース(賃金助成))を活用いただけます。
事前の計画届の提出や訓練後の支給申請など各種の手続きが必須です。詳細は下記をご確認ください。
※令和5年12月作成時点の情報です。最新版は厚生労働省ホームページをご確認ください。
1. 雇用関係助成金について
雇用関係助成金とは ~財源は雇用保険料 ~
雇用関係助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などを実施した事業主または事業主団体に対して支給されるもので、財源は雇用保険料のうち事業主拠出の「二事業」分です(雇用保険料は、従業員と会社が折半して払う「失業等給付」の保険料と事業主だけが負担する「二事業」の保険料とで構成)。
なお、雇用保険料率は建設業の場合、一般の業種より若干高めで、令和5年12月現在、「失業等給付」分が7/1,000 、「二事業」分が4.5/1,000の合計11.5/1,000となっています。
富士教育訓練センターの訓練コースを受講した場合に利用できる雇用関係助成金 ~二つの助成金~
富士教育訓練センター(以下、訓練センター)は、職業能力開発促進法に基づき静岡県知事が認定した職業訓練(認定職業訓練)を実施していますので、従業員に訓練センターの認定職業訓練を受講させた場合は、助成金の申請をすることができます。
対象となる主な助成金として「人材開発支援助成金」のうち「人材育成支援コース」と「建設労働者認定訓練コース(賃金助成)」の二つがあります。
・人材育成支援コース
「人材育成支援コース」は、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するコースで、助成額は次のとおりです。
| 中小企業 | 中小企業以外 | |
|---|---|---|
| 賃金助成 (1人1時間あたり) | 760 円<960 円> | 380 円<480 円> |
| 経費助成 | 45%<60 %> | 30 %<45 %> |
※1 <>内は、賃金 要件・資格等要件を満たす場合に適用されます。
※2 所定労働時間外・休日の訓練を受講した場合や、訓練カリキュラム中に労働安全衛生法に基づく講習が含まれる場合の該当部分が支給対象外となることがあります。
※3 経費助成は、1人当たりの実訓練時間数に対応する支給上限額が定められています。
・建設労働者認定訓練コース(賃金助成)
「建設労働者認定訓練コース(賃金助成)」は、中小建設事業主のみを対象とし、雇用する建設労働者に対して認定職業訓練 を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上の賃金を支払い、かつ人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けた場合に賃金などの一部を助成するコースで、助成額は次のとおりです。
| 中小企業 | |
|---|---|
| 助成額(1人1日当たり) | 3,800円<4,800 円> |
※1 <>内は、賃金 要 件・資格等要件を満たす場合に適用されます。
※2 1事業所・1 事業主団体等が 1事業年度毎に 受給できる助成額の上限 が 1,000 万円と定められています。
受給できる事業主 ~雇用保険適用事業所の事業主~
雇用関係助成金を受給することができる事業主(事業主団体を含みます。以下同じ。)は、各助成金毎に設けられた要件のほか、次の要件すべてを満たす必要があります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
- 支給のための審査に協力すること
- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
- 管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
- 申請期間内に申請を行うこと
受給できない事業主 ~注意すべき10項目~
次の1~10のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、本パンフレットに記載された雇用関係助成金を受給することができません。
- 平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない事業主(平成31年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を経過していない事業主)なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正受給による請求金(※2)を全額納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすることを指します。例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)も不正受給に当たります。
※2 請求金とは、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除く)の合計額です。 - 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合は、受給することができません(※3)。※3 この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や支給決定取消日 から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を全額納付していない場合(時効が完成している場合を除く)は、受給できません。
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に当該労働保険料の納付を行った事業主または納付の猶予期間内に支給申請を行う事業主であって猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主を除く)
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(※4)※4 これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)の雇入れ に係る助成金については、受給が認められる場合があります。また、雇入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は、受給が認められます。
- 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
- 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 管轄労働局長が審査に必要な事項について確認を行う際に協力しない事業主、不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表および請求金(※2)の返還等について、あらかじめ承諾していない事業主
- 支給申請書等に事実と異なる記載または証明を行った事業主
キーワード
中小企業とは・・・
雇用関係助成金の種類により、助成内容が中小企業か中小企業以外かの違いにより異なる場合があります。雇用関係助成金における中小企業は、資本金の額・出資の総額が3億円以下か、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいいます。
雇用関係助成金における建設業とは・・・
雇用関係助成金における建設業は、雇用保険料率が「建設の事業」として適用されているものをいいます。
不正受給の場合の措置
雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように取り扱われます。
- 支給前の場合は不支給、支給後に発覚した場合は、請求金の納付が必要となります。
- 支給前の場合であっても支給後であっても、不正受給による不支給決定日または支給決定取消日から起算して5年間は、その不正受給に係る事業主に対して雇用関係助成金は支給されません。
- 不正の内容によっては、不正に助成金を受給した事業主が告発されたり、事業主名等が公表されることがあります。
2. 雇用関係助成金の手続きの流れ
雇用関係助成金の手続きの流れ ~事前準備を忘れないで~
| ① 受講申込み (一般募集コース 、技能講習 ページの「訓練の申し込み方法について」項目参照) | 募集の締め切りは、訓練開始の原則2 ヶ月前です。 余裕を持った受講申し込みをしてください。 ※訓練開始日の1 ヶ月前よりキャンセル料が発生しますのでご注意ください。 |
|---|---|
| ② 助成金申請のための事前準備 | 【職業能力開発推進者の選出】 職業能力開発推進者は、事業内職業能力開発計画の作成・実施や労働者への適切な相談・指導が行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者を選任してください。(例:教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など) 【事業内職業能力開発計画の作成】 労働局またはハローワークで作成にあたっての相談を受け付けています。 【受給資格の確認】 雇用関係助成金の受給資格があるかどうかを所管の労働局又はハローワークに確認いただくと手続きがスムーズです。 |
| ③ 訓練計画の作成・提出 | 訓練開始日から起算して1ヶ月前までに「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」と必要な書類を各都道府県労働局(ハローワーク)へ提出してください(申請手続きは雇用保険適用事業所単位)。 ※「OFF-JTの実施内容等を確認するための書類」、「訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書」、職業訓練認定証の写しなどは入校案内の際に、受付担当者から送付致します。 |
| ④ 講習の受講 | 訓練修了後1ヶ月を目安に、申請書類の一部(様式第8-1号、様式第12号、建認様式第4号、カリキュラム、職業訓練認定証の写し)を担当者からメールにて、入校案内の中の調査票に入力されたアドレス宛てに送付します。 |
| ⑤ 労働局・ハローワークへの申請 | 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に必要書類を提出してください。(訓練センターから届く申請書類以外にも多くの提出に必要な書類があります) ※建設労働者認定訓練コース(賃金助成)は支給申請のみ行います。 |
| ⑥ 受給 | 労働局・ハローワークでの審査に問題がなければ、指定口座に助成金が振り込まれます。 |
厚生労働省の関係パンフレット
詳しくは厚生労働省ホームページで、以下の各パンフレットの記述を確認のうえ、不明点は所管の労働局・ハローワークに必ずご相談ください。
- 「令和5年度版パンフレット(人材育成支援コース)詳細版(R5.6.26)」で検索
※特にP7、P17、P28、P31、P33、P34が重要です。
P7 不正受給
P17 対象となる事業主
P28 助成額と助成率
P31 手続きの流れ
P33 提出期限
P34 訓練計画届出に必要な提出書類 - 「建設事業主等に対する助成金パンフレット」で検索
※特にP23、P24 が重要です。
※厚生労働省「人材開発支援助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
※厚生労働省「 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html