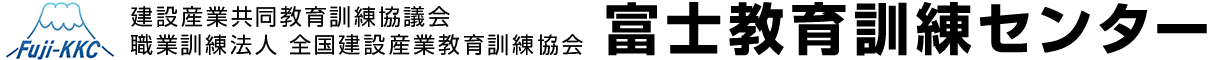前職の経験生かし“短期決戦”に挑む

中央工学校でことし3月まで教鞭をとっていたが定年を迎え、「社会人教育に携わりたかった」と、さまざまな誘いの中から富士教育訓練センターを選ぶ。
「主役は訓練生たち。彼らが安全に実りのある講義・実習が受けられるよう、陰ながら支えていく行動をとりたい」と抱負。
訓練センターを中から見ての感想は。「訓練生たちが将来の希望を胸に、安全を意識しながら行動している姿が非常に印象的でした。また、講師たちの熟練した技術・技能を真剣に受け継いでいこうとしていることにも感動しました」。
とはいえ課題も指摘する。建設大学校時代からの施設の老朽化はやはり目につく。もう一つ。「建設関係の中での知名度が気になる。いかに営業力を上げながら訓練センターを見せていくか、認知させていくかが求められるのでは」と。
ゼネコン職員も例えば足場の上の歩き方やハーネスの痛みなど職人の経験をすることで、職人への指示が重みのあるものになると考える。「現場は代理人から職人までが一丸となって進められる。それをできるのが訓練センターの強いところ」と語る。だから「そうした存在価値を知ってもらえるよう営業の部分で何かできればと思っています」。
専攻は設備(空調)だが、「建築が分かっていないといけない」と上司に言われ建築士を取得。さらには学会設備士、消防設備士、小型車両系建設機械運転、福祉住環境コーディネーターなどの資格も持ち、「何が専攻か分からなくなってきた」。
「勉強が苦手だった学生が授業を受けて興味を持ち目の色が変わる。受講態度が前のめりになるのを見ると、教えていて良かったとやりがいを感じていました」。根っからの教育者。また「紙の上だけの理解は嫌い。実際に手を動かし、物に触れることでどう感じたかを考える教育を推奨してきた」は訓練センターの教育訓練そのものだ。
ただ、前職との違いで大きいのは、学生とは信頼関係を築く時間があったが、訓練センターでは「短期決戦。短い期間でどこまで信頼関係をつくりながら、建設業界でやっていける人を育てていけるか。前職で考えたこと、感じたことを生かせたらなと思います」。
母親から何度も言われてきたのは「『相手の気持ちになって話せ。その言葉を言って相手がどう感じるかを考えてから言葉を発しろ』で、自分の言葉では『人が人を育ててくれる』の原点にある。いろいろなことを学生からも教えられてきた」。教える側も教えられる側でもあるという謙虚な姿勢をいつも忘れない。
学生が取得を目指す資格ごとのグループラインを設けて、相談や質問に答えていたため、「365日仕事だった。学生が結果を出してくれることに喜びを感じていた」と自分で言うほど。だから趣味はなく、「子どもから『趣味を持とうよ』と言われる」。そこで昔、好きであったバイクを、リターンライダーとして再度乗り始めた。ただし、今はすり抜けにはブレーキが掛かるそうだ。

加賀美武専務理事は、近年若手職員を採用し訓練センターに新しい風が吹き始めている中で、今回の中村氏の教務部長就任が「時代の変化に対応する組織体へと生まれ変わる上で強い風となる」と大きな期待を寄せている。