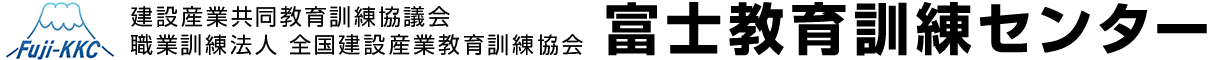需要掘り起こしに注力
小松原学前校長らが退職し、 4 月に富士教育訓練センター校長に就任した米良力氏(前教務課長)。専務理事と共に、教育訓練の前線指揮官も大幅に若返りました。少子化など富士教育訓練センターの行く手に山積する課題にどのように立ち向かうのでしょうか。インタビューしました。

― まずは抱負を。
「社会情勢は大きな変革期に入っていると思います。小松原前校長がパラダイムシフトとよく話していましたが、その通りだと実感しています。変革期の中でバトンを引き継ぐ新体制となり、激動の時代をどう運営しなければいけないのか難しい判断になろうかと思いますが、粉骨砕身、センターの安定的経営に努めていくつもりです。関係各所におかれましては、今後ともご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。」
― どのような運営を目指しますか。
「私なりにいくつかの施策を考えています。短期目標もさることながら、DXの進展など建設技術・技能に新たな取り組みテーマが発生していることから、中・長期目標となるロードマップの作成が必要と考えています。安定経営に欠かせない構成要素として①新規受人コースの開拓、②助成金、③年代別人材確保などがあります。特に、バーチャル化やオートメーション化の中で技能、教育訓練の在り方が大きく変わる可能性もあり、注視していかなくてはなりません。」
― コロナ禍前の人日数に戻りませんね。
「建設産業を取り巻く課題として人材確保が一番に挙げられます。日本の生産労働人口(15~64歳)の減少が顕著です。これは富士教育訓練センター(以下訓練センターという)にも直接かかわる課題です。訓練センターの利用者は若年層(15~34歳)が大半で、出生数が利用者に直結します。既に影響が表れ始めているのではないかと受け止めています。訓練センターの認知度はまだまだです。広報次第では潜在需要を掘り起こし、訓練生の送り出し企業を増やすことは可能だと考えます。広報活動は遅効性の薬として、職員一丸となって継続的に広報活動を進めていきます。」