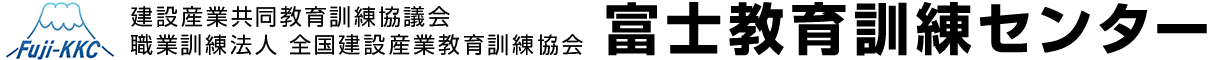富士教育訓練センターでは、講師・職員向けのメールマガジンを原則月2回発行しております。これには巻頭文の形で、専務理事はじめ訓練センター全職員が、講師・職員に伝えたいことなど、さまざまなテーマで文章を寄せています。本欄は、この巻頭文を転載するものです。ぜひ、ご一読ください。
訓練センターの「あり方」を明確化する
9月11日(木)、講師と職員対象のハラスメント・アンガーマネジメント研修を、建設産業研究所の齋藤昭彦氏を講師に招き、訓練センターで開催しました。参加いただいた講師の皆さまにはお役に立ちましたでしょうか。講義の中で、怒りを感じたら…「6秒数えてみる。深呼吸で気持ちを落ち着かせる」「趣味や好きなスポーツなど気持ちの良い瞬間を思い浮かべる」「タイムアウトする」などの対処法を指導いただきました。
私自身は、感情のコントロールは非常に難しく、いざ激昂している中でこうしたことが思い浮かんで実行できるか? 私には修業が必要と感じたところですし、講義を聞いて本当に気を付けなければならないと自戒しています。
今回の研修でいくつかのキーワードをいただいたので、自分なりに復習を兼ねて調べてみました。最近のリーダー論はシチュエーショナル・リーダーシップ理論という考え方で、リーダーは部下を4つのタイプに分けそれぞれに最適なリーダーシップを示す指導法です。また、コミュニケーションの取り方では、アサーティブ・コミュニケーションという考え方。これは、「自分と相手の両方を大切にし、攻撃的でも受動的でもない適切な主張を行う」というもので、アイ(i)メッセージ・ユウ(you)メッセージなど、自分・相手のどちらを主語として表現するかといった話法の一つです。
こんなことをあらためて調べていると、「内省」、「反省」というキーワードが出てきました。「内省」とは、外の出来事や他人の言動をそのまま評価する前に、まず自分の内側にある感情や思考を観察する作業を指します。「内省」の目的は自分の心の状態を理解し、次にどう行動するかを選ぶ力を育てることにあります。
これに対して「反省」はご存じの通りです。「やり方がまずかった」と「反省」します。もちろん「やり方」も大事です。仕事はもちろん、何事も正しい手順で行わなければ、正しい結果を得ることは難しいでしょう(結果オーライはダメ)。しかし、「やり方」が良ければいいというわけでもありません。むしろ、「やり方」以上に「あり方」が大切だと記されていました。
何をするにも、まず、どうあるかが大切です。「訓練センターのあり方」「教育訓練のあり方」「職員のあり方」「講師のあり方」などなど。私の仕事はさまざまな「あり方」を明確にし、それを皆さんと共有して建設業に携わる技術者・技能者の方々の育成に熱意をもって取り組んでいただける場をつくることです。時間はかかりますが、皆様と力を合わせ進んでいきたいと感じたところです。