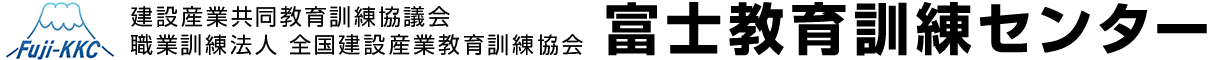国土交通省国土交通大学校(山田哲也校長)は4月2日、令和7年度国土交通省総合職技術系新規採用者研修(建設技能実習)を静岡県富士宮市の富士教育訓練センターで実施しました。参加者は73人。実習は①荷物の吊り上げ安全作業体験、②建設機械の安全作業体験、③墜落制止用器具による安全体験―の3種類を行いました。訓練センターでの研修は今回が4回目となっています。

この研修は、新規採用者が地方等に配属されるに当たって、訓練センターでの実習を通じて建設現場で必要とされる基本的な技能・技術について学ぶとともに、建設業界の建設技能者・技術者の人材育成・人材確保の取り組みに対して理解を深めることが目的。
入校式では、山田校長が「専門工事業者の方々が力を発揮していただいて、国交省の仕事が全うできる。単に発注者という立場ではなく、地域を守る、地域の暮らしを良くするパートナーとして、地域の建設業の皆さんと良い関係を築いてほしい」と話しました。また、今回の研修を通じて「現場でどういうことを生身の人間がやっているのかをしっかりイメージしながら仕事に取り組んでほしい」と呼び掛けました。

続いて、山梨敏幸全国建設産業教育訓練協会会長があいさつ、「発注者、ゼネコン、専門工事業者の3者がお互いにリスペクトしていないと絶対に良い物はできない」と訴えた上で、「専門工事業者は夏の暑さ、冬の寒さ、雨の冷たさ、フルハーネスの重さなどに耐えながら生産に携わっている。きょうはそういう体験をしてもらうことで、専門工事業者の立場を分かってもらえればと思う。この実習は皆さんにとって必ず有益なものになる」と話しました。
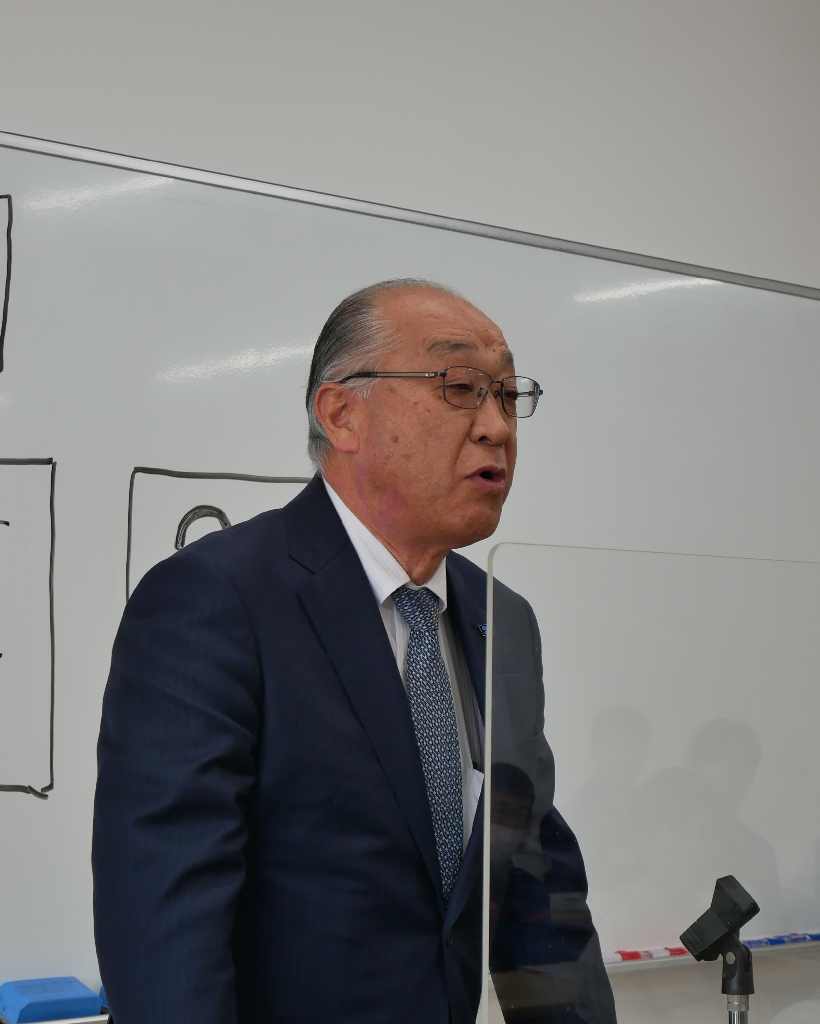
実習では、3班に分かれて、①荷の吊り上げ安全作業体験・玉掛け・小型移動式クレーン、②建設機械の安全作業体験、③墜落制止用器具による安全体験―をそれぞれ約50分かけてローテーションする形で行われました。
荷の吊り上げ安全作業体験では、玉掛けの重要性や小型移動式クレーンの構造、ワイヤーロープについての説明と実演。講師が、玉掛けとはどのような作業であり、どのような危険が潜んでいるかを分かりやすく説明しました。

建設機械の安全作業体験では、班員を3班に分けて、大型、中型2台のバックホウとタイヤショベルの3台の試乗などを体験しました。大型バックホウでは、運転席から死角を確認しバックホウの危険について学びました。班員をバックホウの周りに配置し、運転席から見えるかどうか確認。講師は「重機の近くで作業する際は、自分の存在をオペレーターに気付いてもらうことが大事」と説明。中型バックホウでは、基本的な操作としてアームやバケットを上下に動かしました。ゆっくり慎重に動かす人、素早く動かす人と違いがありました。タイヤショベルは高い 位置にある運転席を体験しました。

墜落防止用器具(ハーネス)による安全体験では、フルハーネスと胴ベルトを装着し、墜落防止器具の重要性を実感するとともに、墜落防止器具によって命の安全は確保される一方で、体に相当の負荷がかかることを体験しました。

国土交通大学校の鳥山仁建設部建設企画科長は、「彼らはこれから全国の(地方整備局などの)出先事務所等に配属される。今回の研修で基礎を学んだことで、心理的にも現場に出るハードルが下がったと思う。デスクワークも少なくないが、研修の経験を元に、現場にも積極的に出て行ってほしい」と感想を述べました。
実習修了後、建設業者等とのコミュニケーションに役立ててもらおうと、訓練センターから参加者全員に訓練センター卒業生がヘルメットに貼るシールを配布しました。
当日は、曇りがちながら春らしい陽気でしたが、実習の終わり近くから天候が急変し、冷たい雨の中の実習となりました。それでも参加者は最後まで熱心に取り組みました。