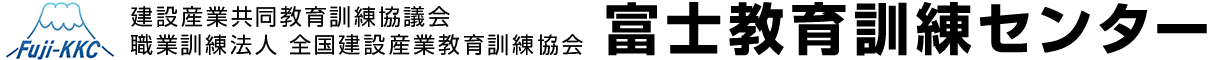富士教育訓練センターは8月19日、20日の2日間、(公社)日本建築士会連合会(士会連、古谷誠章会長)の建築技術委員会部会メンバーと建築系人材の育成など幅広いテーマで初の意見交換会を開きました。訓練センターの教育訓練について、特に士会連側からは、「施工管理者としても技能を体験することが大事であり、身をもって知ることに価値がある。」といった意見が出されました。
士会連側は、建築技術委員会の監理技術者講習テキスト作成、建築施工系技術者育成の両部会メンバーと事務局計11名、訓練センターからは加賀美専務理事をはじめ3名の職員、建築系講師ら2名参加。この他、建設業振興基金の長谷川周夫専務理事、建設産業専門団体連合会の柳澤庄一専務理事も出席し、総勢18名で打合せを行いました。
訓練センターでは建築施工の講義に使用するテキストについて、士会連に一昨年から協力を仰いでいました。士会連としても、建築生産の現場で分業化が進み、施工系の人材育成が課題となっていたことから、今回、両者が意見交換をして今後の人材育成の在り方を探ることにしました。
開会に当たって、米良校長は「コロナ禍以降は積極的な営業が必要」とするとともに、「危機感を職員と共有しながら進んでいきたい」とあいさつしました。続いて、参加者が訓練センターとの関りなどを交えて自己紹介をしました。
この後、話題提供として米良校長が訓練センターの取り組みを、また中島芳樹士会連建築施工系技術者育成部会長が同部会の活動をそれぞれ紹介しました。中島部会長は「近年、大学生などの施工系志望者が少なくなっていて危機感が大きい。施工系技術者・技能者の育成・教育について効果的な施策を模索している。訓練センターと一緒に活動できないか。」との話がありました。
意見交換では、訓練センターに対する意見や要望が相次ぎました。例えば、「技能者の先生自体に価値がある。訓練センターを残していくべきだ。」「(ゼネコン社員が)現場の疑似体験を行うことで現場への恐れがなくなる。研修後のアンケートで大半が技能者の仕事をやりやすくすることが技術者の仕事だと分かった。技能者は尊敬すべき人たちだと答えた。」と高く評価されました。さらに、「技術者と技能者が一体となって受講し、人間力を高める教育ができないか。」という要望も出されました。
訓練センター側から現在直面する課題としてハラスメントが話題に上る中、「訓練センターとしてサブコンの社長向けにパワハラの研修をすればいいのではないか」という提案がありました。
米良校長が訓練センターの活用促進に向けて潜在需要の発掘が必要だと訴えたのを踏まえて、長谷川専務理事「中小企業の技能者に教育訓練が不足しているのではないか。どこにどういう教育訓練が不足しているのかを全体を眺めて探るべきだ。どこにターゲットを置いて目指すべきかを関係者が皆で考えることが大事だ」との意見がありました。
開催期間中、訓練センターで鉄筋コンクリートの実習をしている建築系大学の学生10人との意見交換も行いました。4年生が6名、3年生が3名、1年生が1名で3つの大学から受講生が集まりました。相互の自己紹介を行い、学生からは「ゼネコンに就職する予定だが、この実習を通して職人さんへのリスペクトが生まれた。この気持ちを忘れず職人さんと接していきたい。」などのコメントがありました。
終わりに、中島部会長からの「非常に有意義な会となり、継続的に行いたい。生産設計ガイドラインの策定に併せてテキスト作成なども考えており、人的にも協力いただきたい。」という要望を受け、全国建設産業教育訓練協会の加賀美武専務理事が「中核的なセンターとしての位置づけもあり、協力していきたい。」と答えました。