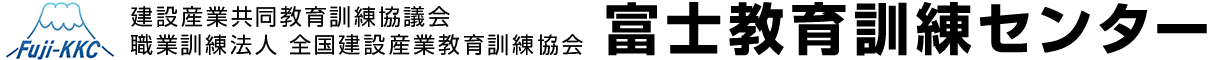全国建設産教育訓練協会、富士教育訓練センターは9月11日、静岡県富士宮市の富士教育訓練センターで、ハラスメント対策とアンガーマネジメントをテーマに令和7年度の職員・講師研修会を開きました。講師は、ことし1月の研修会に続き、日本コンサルタントグループ・建設産業研究所の齋藤昭彦氏が担当しました。齋藤氏は、講師の訓練生への教え方が建設業の人手不足対策につながるという観点から、「人手不足や離職者の多さという課題に対する認識を持ってほしい。伝え方改革をしていかなくてはならない」と呼び掛けました。

研修には、講師・職員など計約50人が参加。4人ずつのグループに分かれ、講義の要所要所で課題が出されるたびにグループで話し合い、その結果を発表する形で行われました。
まず、講師の訓練生との接し方として、普通科の高卒者や文系の大卒者が採用されている現状を踏まえて、「シチュエーショナルリーダーシップ理論」を紹介、「受講生の意欲や知識レベルによって指導法、スタイルを変えることが有効だ」と指摘しました。
パワーハラスメントについては、齋藤氏は、講師は能力や経験、知識などがあって「自動的に優越的立場に立ってしまう」、同時に「ハラスメントと判断するのは行為を受けた側である」ことから、業務上必要かつ相当な範囲を超えない、労働者の就業環境を害さないような行動に心がけるよう注意を促しました。
訓練生を注意したり、叱る際には、「AID」で対応するべきだとし、事実や行動に基づいて指摘する(A=アクション)、それによって発生した影響を説明する(I=インパクト)、そして今後の改善方法を伝える(D=デベロップメント)という方法を紹介。
また、セクシャルハラスメントでは、「意図しない言動が相手の感じ方によってはセクハラに取られてしまう」ことがあるため、「性に関わる言動そのものをできるだけ排除すること」が予防策だと説明。さらに、LGBTにも触れ、多様な個性を持つ人が周りにいることを理解し、「これまで以上に気遣いをしていただきたい」と訴えました。
アンガーマネジメントは今回新たなテーマとして取り上げたもの。齋藤氏は、怒りが他の感情から引き起こされる2次感情であるとし、自分の怒りが生まれるメカニズムを自身で見つめ直してみることを勧めました。怒りを防ぐために、自分自身の価値観で決めつけないこと、自分の行動や経験に自信を持つこと、新しいことや違ったことに対して「学び」や「気づき」を見つける―の3つのポイントを理解し、組織や人脈、行動で「思い通りにならないというネガティブな不安を和らげる」よう求めました。
当日の研修の主要テーマを踏まえ再度、注意の仕方、叱り方について触れ、「アサーティブコミュニケーション」という方法を紹介。相手に迎合する、あるいは甘やかすのではなく、「自分のことをまず考えるが、相手にも配慮する考え方」だとして、①主語には必ず「私は」とつける、②判断の成功、失敗にとらわれないこと、③言わないこと、奥ゆかしいことは美徳ではない、④自分の考えや感情のクセを知る、⑤相手と普段からコミュニケーションをとり、考え方のクセを知る―の5つのポイントを挙げました。
齋藤氏は、「訓練生に意欲やモチベーション、達成感や成功体験を持たせ、教えたことを現場で生かしてもらうという講師としてのゴールを見据えてほしい」と講義をまとめました。