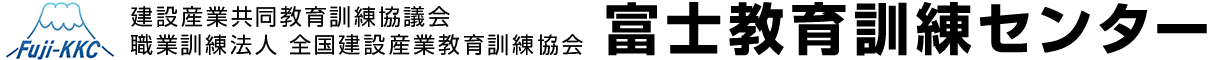建設経済研究所の佐々木基会長は、10月28日に開かれた日本建設躯体工事業団体連合会(略称・日本躯体)の創立50周年記念式典で、「今後の建設業の展望について」と題して講演しました。今後の職業訓練のあり方に触れ、「一企業、一団体で職人を育てることが難しくなっている。より大きなシステムを作らなくてはならないと思っている」とするとともに、「もう『背中を見て学べ』は通用しない。システマチックに育てることが必要だ。できれば国を挙げて取り組んでほしい」と提案しました。
佐々木会長は、平成から令和にかけての建設投資を概観し、建設投資がピーク時から大きく減少した時期に「人も去り会社もつぶれた。その影響が今も続いている」とした上で、インフラの老朽化や災害の激甚化・頻発化には「日頃から(建設業者が)人を抱えていないと対応できない。一定の仕事量、地域に貢献する事業をやっていないと対応できない」と指摘しました。
建設業就業者の推移について、「技術者は若干増加傾向にあるが、技能者が猛烈な勢いで減少している」ことや、高齢化が進行している状況をあらためて確認。特に建設投資が抑えられた時期の年代の技能者の少なさは「どうやっても埋めることはできない」ため、今後10年後を見越してより若い世代の人たちを増やすよう、小中学生などに「建設業の重要性や魅力を提供していくことが重要」と訴えました。
社会全般の傾向として建設業の本質を知らないで勝手にイメージを作り上げている側面があることから、若年層の入職を取り戻すため、「良いイメージを持ってもらうよう、重機に触れるなど多少でも経験をしてもらうこと」が必要と述べました。さらに、「われわれが3Kと卑下していたらダメで『格好良くて稼げる』と言えるようになっていかなくてはならない」とし、建設キャリアアップシステムの最上位の人で1000万円~1500万円といった、高い給料をもらうスーパースターを生み出していけば、周りに与える影響は違う。こういうことを考えてほしい」と呼び掛けました。
建設業の賃金については上昇傾向にあるとはいえ、賃金決定の流れを川上から川下ではなく、逆に下請けから元請け、発注者という流れにしなくては「建設業の賃金は低いままであり続けると思う」と述べました。
佐々木会長は、AIにとって代わられずに残る仕事に建設作業があるとし、そうした「AIが進んでも人間がやらなくてはできない仕事、エッセンシャルワーカーの仕事として価値が上がってくる」と話しました。さらに「手に職を持っている職人が認められていく時代が来るのではないかと期待している」と、講演を締めくくりました。