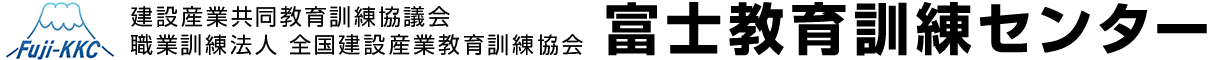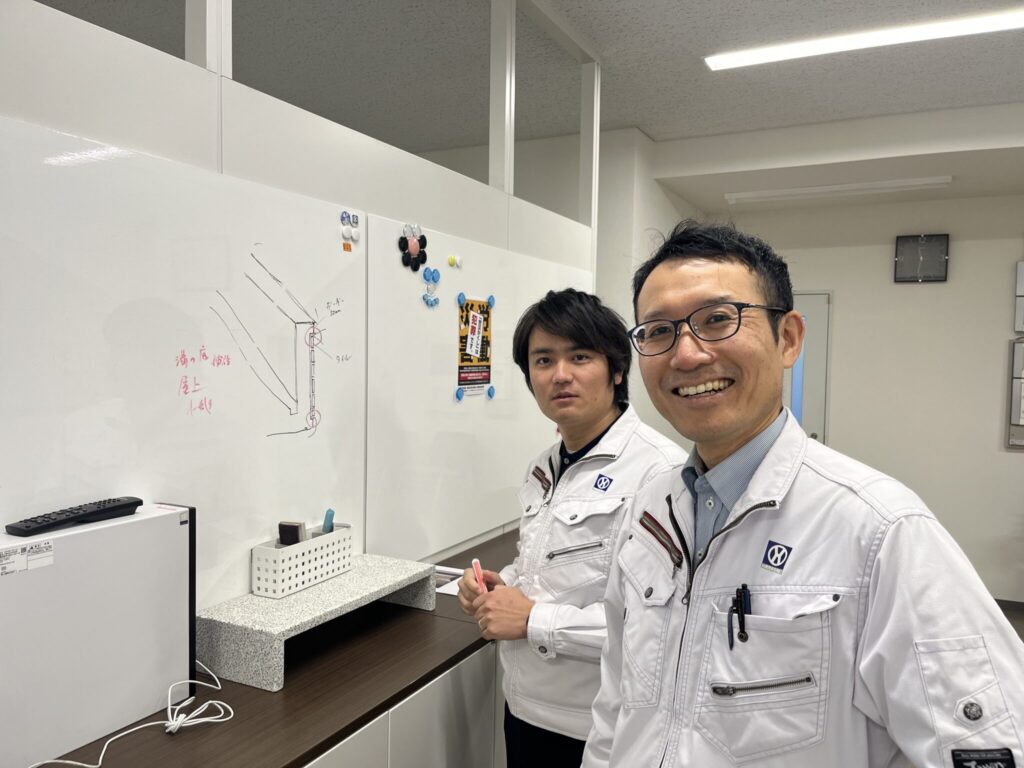Q. 富士教育訓練センター(以下、訓練センター)の教育訓練を利用する目的をお聞かせください。
現在、躯体や足場実習など実際に触れて見て学べる機会というのは、現場に入ると作業をしながら学ぶことになるため、落ち着いて体系的に学ぶ機会というものはありません。自社でその場を用意することは難しいということから、現場に入る前に訓練センターで学び理解を深めてほしいのです。
また、一度見たことだとしても現場員毎に教育基準も異なっており、そのレベルを統一して学ばせる機会を持たせたいという意図があります。
さらに、資格取得も行っておりますが、費用は掛かるものの、実際に手配する側としては手間が大きく減り、現場状況による不参加等も無く統一して取得させられるメリットもあります。
Q. 訓練修了後、受講された訓練生に送り出し前と比較し、変化したと感じたことはありますか。
「研修で学びました」という声が挙がるなど、躯体関係ではこちらが教育をする前にある程度の基礎を身に着けてくれていることがあります。また図面の読み方などは、普段は(なかなか時間を作れないのですが)この研修を通して同じく基礎(正解)を学ぶことができているなと感じる場面があります。
また、現場配属を数か月行いその後訓練センターにて同期と共に過ごす時間を持つことにより、本人たちの心のリフレッシュにもつながっている効果も感じます。
Q. 訓練カリキュラムが、実際の業務に役立っていることは何かありますか。
躯体実習においては、配筋検査等での理解が深まり、自ら考えある程度行動できるようになっていること、図面理解においては、現場で「知らなかった」が減ったことにより初歩的な間違いが減ったことが挙げられます。
Q. 訓練センターの利用前と利用後で、どのような変化がありましたか。
現場配置になると現場配置の上司から教育を受けますが、その上司によって教育レベルがバラバラになってしまいます。しかし、配置後に改めてこのように研修を受けることで、ばらついた意識も改めて統一する機会になっている効果を感じます。


| 社名 | 加和太建設株式会社 |
| 所在地 | 静岡県三島市文教町1-5-15 |
| 電話番号 | 055-987-5541 |
| ホームページURL | https://www.kawata.org/ |
| お問い合わせ先 | 090-6383-2298(岡田) |
| 主な営業種目 | 総合建設業 |